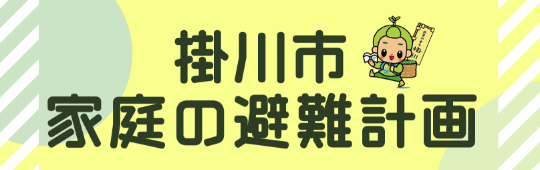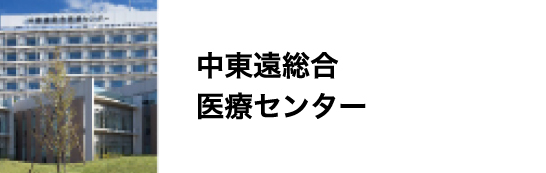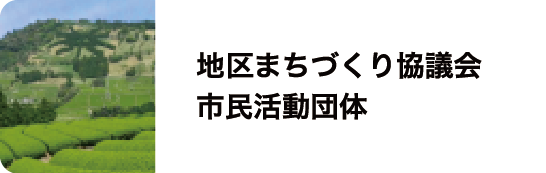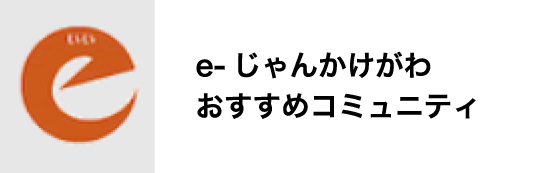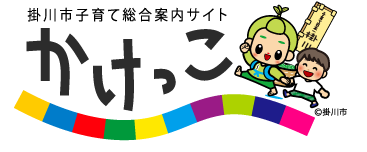小中学校の再編や統合についてよくいただく御質問と回答についてまとめました
小中学校の再編・統合についての説明会や会議の際によくいただく御質問とその回答についてまとめました。
市内全域にかかわる御質問と回答
Q10:再編に着手する順番はどのようにして決まったのですか?
Q11:施設について、再編計画が後ろの年次の学校は耐震や老朽化対策は大丈夫ですか?
Q12:中学校区ごとに一貫校をつくる方針はどの学園でも同じなのですか?
Q14:新しい学校に公共施設を併設するとき、セキュリティ面で問題はないの?
Q19:再編や統合の際に、子どもが新しい環境に馴染めるのか心配です。
Q20:再編や統合によって閉校となった学校跡地の利活用はどうなりますか?
Q21:学校がなくなることで、広域避難所がなくなってしまうと不安です。
Q22:再編や統合にともない地域コミュニティ(地区組織)も再編・統合されるのでしょうか?
| Q1 | なぜ学校再編を進めるのですか? |
| A1 | 学校再編を進めるには、(1)新しい学力観、授業観への対応、(2)少子化への対応、(3)学校施設の老朽化への対応が大きな目的となります。詳細はこちらをご覧ください。 |
| Q2 | 学校の再編・統合は決定事項ですか? |
| A2 |
個々の学校の再編・統合は決定事項ではありません。教育委員会としては、これから子どもたちに求められる学力を育むために、仲間との議論や学びあいを実施できるような望ましい環境を、 学校再編を通して整備したいと考えています。ただ、地域における学校の役割や、学校の思いを考えた時、決定事項としてお示しするのではなく、地域の皆様との対話を通して、 子どもたちにとってどのような教育環境が望ましいかを検討したいと考えています。 |
| Q3 | なぜ小中一貫教育を進めるのですか? |
| A3 | 小中学校の9年間で共通の教育目標のもと、一貫したカリキュラムで子どもたちが学ぶことができます。学習面での小中学校間の円滑な接続が子どもたちの学力の向上に繋がります。 |
| Q4 | 施設一体型の小中一貫校はどんな点がいいのですか? |
| A4 | 小中学生が同じ施設で生活することで、小中一貫教育の効果をより高めることが可能です。 先に挙げた学習面での効果の他、中学校への進学時の環境変化を軽減することで学校間のギャップに適応できずに苦しむ子どもを減らすことが可能です。実際に不登校が減少することが分かっています。 また、異学年の交流が増えることによって子どもたちの自尊感情を高めることができ、特に中学生の生活が安定する学校が多いです。 さらには、小学校の教員と中学校の教員が一緒に働くことで、それぞれの教え方の良い点を学びあったり、より多くの教職員の目線で子どもたちを見守ることが可能になります。 |
| Q5 | 小規模校には小規模校の良さがあるのではないですか? |
| A5 |
小規模校では、一人一人の子どもに教員の目が届きやすく、一人の子どもに多くの活躍の場が与えられる、少人数であることから親密な人間関係が構築できると言った良い面があります。 他方で、多様な仲間の中で様々な価値観や考えに触れる機会が限られてしまうという点もあり、良い面、悪い面を考慮しながら、将来の子どもたちの教育環境がどうあるべきか考える必要があります。 |
| Q6 | 学校教育において適正規模とはどれくらいの規模ですか? |
| A6 |
クラス替えができる1学年2学級以上が理想ですが、1学年が1学級であったとしても、少人数のグループを複数組むことのできる20人以上が望ましいと考えています。仲間との議論や学びあいを行うにあたり、 多くの考え方や意見に触れることができ、様々な役割を担うことが可能になる人数が適正と考えています。 |
| Q7 | 学校再編はどのように進めるのですか? |
| A7 | 今後、令和5年8月に策定した掛川市学校再編計画に基づいて今後30年間をかけて市内の小中学校を小中一貫校に再編していきます。 |
| Q8 | いつごろ学校を再編するのですか? |
| A8 | すべての学区の再編を同時に進めることは困難であることから、中学校区ごとに検討に着手する順番を決めて、その順位にもとづいて再編の検討を進めていきます。 市内9中学校区を10年間で3校ずつ、再編していく計画です。 1期(令和5年~):原野谷、城東、東 2期(令和15年~):栄川、桜が丘、大浜 3期(令和25年~):西、北、大須賀 |
| Q9 | 学校再編・統合にかかる時間はどれくらいですか? |
| A9 |
地域との協議を2年間、再編・統合の実施について合意後に、学校再編の場合には5年間、学校統合の場合には2年間の準備期間を経て、 再編・統合を完了させるのが最短のスケジュールとなります。 |
| Q10 | 再編に着手する順番はどのようにして決まったのですか? |
| A10 | 小中学校の校舎の老朽化の状況、児童・生徒数の増減の状況、災害の発生の危険性 等を参考に、優先して検討を行う必要がある学園から順番を割り振っていきました。 |
| Q11 | 再編計画が後ろの年次の学校は耐震や老朽化対策は大丈夫ですか? |
| A11 | 耐震については、国が指定する耐震基準を満たすように、全学校の校舎及び体育館の耐震工事を完了しています。老朽化について、多くの校舎が築40年以上を経過しており、雨漏りなど様々な課題が出てきている状況です。再編まで何も対応しないということではなく、再編までの使用年数に応じて、長寿命化のための大規模改修工事等を計画的に実施して、安全性や機能性の確保を図っていきます。 |
| Q12 | 中学校区ごとに一貫校をつくる方針はどの学園でも同じなのですか? |
| A12 | コロナ禍以降、出生数が急激に出生数が減少しており、今後、現在の中学校区単位一貫校を整備していくことが困難になることも考えられます。学区や学校施設のあり方については、地域の皆さんとの協議の中で決定していきたいと考えております。 |
| Q13 | 学区が変更になる可能性はありますか? |
| A13 | 地域との協議のスタートは中学校区単位で開始しますが、要望があった場合には学区に隣接する地区地域の皆様の御意見も伺いながら検討を進めたいと考えています。場合によっては、現在の中学校区を超えて学区の再編を行う可能性もあります。 |
| Q14 | 新しい学校に公共施設を併設するとき、セキュリティ面で問題はないの? |
| A14 | 公共施設を併設する場合にも、出入口や動線を学校用と地域開放用に区分するなどして、安全の確保を図っていきたいと考えています。先進事例を参照にしつつ、運用方法については地域の皆様と検討の上で決定していきます。 |
| Q15 | 建設費用はどうするのですか? |
| A15 |
掛川市内の小中学校の施設は、昭和40~50年代に整備されたものが多く、築50年以上経過している施設が過半を占めます。今後、これらの施設の更新や大規模改修工事が必要となりますが、将来の人口や子どもの数の推移を考えると、現在の市内の小中学校(小学校21校、中学校9校)をすべてを維持しながら、更新や改修を行っていくことは財政的な負担が大きく困難になっていくものと思われます。 |
| Q16 | 再編することで通学距離が長くなることが心配です。 |
| A16 | 遠距離を通学する児童については、市の費用負担で公共交通機関やスクールバスを使って通学しています。現状、小学生については学校までの距離が4キロメートル以上の場合を通学支援の対象としていますが、統合・再編により3キロメートル以上4キロメートル未満の1時間以上かけて学校まで徒歩通学をする児童も増加することが想定されることから、通学支援の基準の緩和について、現在検討を進めているところです。 |
| Q17 | 小学生と中学生が一緒に生活することが心配です。 |
| A17 | 小学生が中学生と一緒に生活することで、中学生からいじめを受けたり、悪い影響を受けるのではないかと心配される保護者が多くいらっしゃいますが、施設一体型一貫校で小中一貫教育に取り組んでいる他市の学校のお話を伺うと、ほぼすべての学校で、中学生は小学生のことを思いやるようになり、普段の生活の中でも様々な配慮を示すようになる、中学生が小学生のお手本になろうとする意識が強くなり、中学生の生活態度が良くなったという意見がたいへん多く聞かれました。一体型の校舎で、小中学生が一緒に生活することで中学生にも、小学生にも大きなメリットがあると考えています。 |
| Q18 | 9年間同じメンバーで生活することが心配です。 |
| A18 | 中学校区内の小学校を再編することにより1学年の児童数が増加します。1学年に複数の学級が編制されることによって、定期的にクラス替えを行うことが可能となり、クラス替えを行うことで人間関係をリセットすることが可能になります。小規模な学校で6年間クラス替えがなく同じメンバーで学校生活を送るより、9年間で全体としては同じメンバーではあるものの、クラス替えでメンバーの変更が可能である方が、人間関係の固定化の解消や、多くの仲間の中で多様な意見や価値観に触れることができ、教育的には大きな効果があると考えています。 |
| Q19 | 再編や統合の際に、子どもが新しい環境に馴染めるのか心配です。 |
| A19 | 掛川市では、中学校区単位での小小交流(小学校同士の交流)や小中交流(小学校と中学校の交流)を小中一貫教育の一環として積極的に行ってきました。再編や統合を行う際には、事前交流の回数を増やして、円滑に新しい環境に移行できるように準備を進めていきます。また、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった専門職とも連携しつつ子どもたちの心のケアに努めていきます。 |
| Q20 | 再編や統合によって閉校となった学校跡地の利活用はどうなりますか? |
| A20 | 閉校後の学校跡地については、まずは市役所の内部で利活用をしたい部署はないか、それがない場合には地域として利活用の意向はないか、地域ので活用意向がない場合には、地域の御意見を伺った上で、民間の事業者や団体に利活用の意向がないか調査をかけていく予定です。 |
| Q21 | 学校がなくなることで、広域避難所がなくなってしまうと不安です。 |
| A21 | 閉校後も施設が残っていて広域避難所としての利用が可能な間は、広域避難所として活用するというのが市としての方針です。 |
| Q22 | 再編や統合にともない地域コミュニティ(地区組織)も再編・統合されるのでしょうか? |
| A22 | 地区組織(地区区長会、地区まちづくり協議会)は、それぞれの地区の自治的な組織であり、市がそのあり方についてこうするべきとお伝えする性質の組織ではないと考えています。学校の再編・統合にあわせて地区組織を再編するのかについては、それぞれの地区で検討・判断をお願いします。 |
原野谷学園に関すること
Q4:一貫校を開校してもすぐに小規模な学校になってしまうのでは?
| Q1 | 一貫校はどこに建てるのですか? |
| A1 | 現在の原野谷中学校の敷地に建設します。 |
| Q2 | 一貫校の建設地はどのように決まったのですか? |
| A2 |
令和5年度に原野谷学園新たな学校づくり検討委員会で候補地を選定していただきました。この委員会は、地区役員、保護者代表、学園のコーディネーター、園長、学校長等で構成された委員会です。3つの候補地を各委員が一人づつ評価を行い、委員が評価したものを集計した結果、最も得点が高かったのが原野谷中学校の敷地でした。この結果を受けて、教育委員会、掛川市で検討を行い、掛川市としても原野谷中学校の敷地に一貫校を整備することを決定しました。 以上の経過については、こちらに掲載してありますのでご覧ください。 |
| Q3 | いつ開校するのですか? |
| A3 | 現在、考えている最短のスケジュールでは令和11年4月の開校を予定しています。 |
| Q4 | 一貫校を開校してもすぐに小規模な学校になってしまうのでは? |
| A4 | コロナ禍以降の出生数の減少が進んでいます。教育委員会では、(仮称)原野谷学園小中一貫校の将来的な少人数化を見据えて、学年の枠を越えた異年齢の集団による学びや活動を行い、自律と共生を学ぶイエナプラン教育の導入について研究を進めるとともに、市内の他の学校区からも通学が可能な通学区の弾力化についても導入を検討しています。 |
| Q5 | 現在の状況は? |
| A5 | 令和7度から設計業務に着手します。 令和7年7月に設計業者が選定されました。 |
城東学園に関すること
| Q1 | 一貫校はどこに建てるのですか? |
| A1 | 東京女子医科大学掛川キャンパスの跡地に建設します。 |
| Q2 | 貫校の建設地はどのように決まったのですか? |
| A2 | 令和6年度に城東学園小中一貫校整備検討委員会で候補地を選定していただきました。この委員会は、地区役員、保護者代表、学園のコーディネーター、園長、学校長等で構成された委員会です。3つの候補地について各委員が一人づつ評価を行い、委員が評価したものを集計した結果、最も得点が高かったのが東京女子医科大学掛川キャンパスの跡地でした。この結果を受けて、教育委員会、掛川市で検討を行い、掛川市としても東京女子医科大学の跡地に一貫校を整備することを決定しました。 |
| Q3 | いつ開校するのですか? |
| A3 | 現在、考えている最短のスケジュールとしては令和12年4月の開校を想定しています。 |