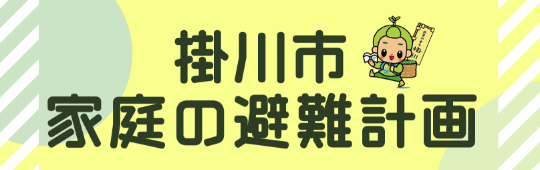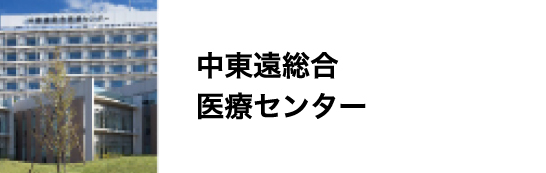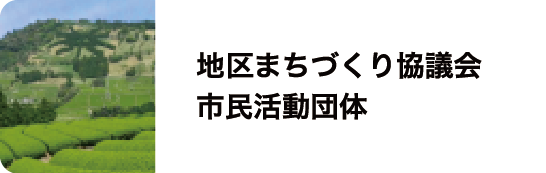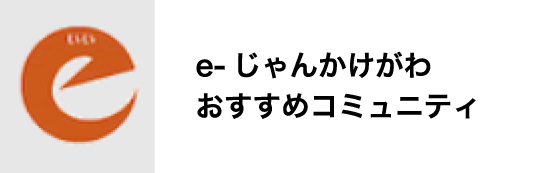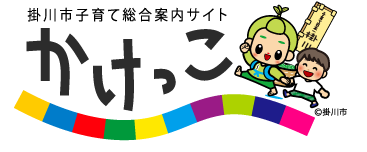掛川市健康福祉部付参与
掛川市・袋井市病院企業団立中東遠総合医療センター
経営管理部長 兼 管理課長 岩井 政昭
中東遠総合医療センターは、掛川市・袋井市をはじめとする中東遠医療圏(掛川市・袋井市・磐田市・菊川市・御前崎市・森町)47万人の基幹病院として、地域連携のもと住民が必要とする急性期医療の提供に努め、開院後5年目を迎えました。
今回は、団塊の世代が後期高齢者となる平成37年(2025年)に備え、今後、増大する医療需要に対応し、地域に必要となる医療提供体制を将来にわたり確保することを目的に平成27年3月、総務省より示された「新公立病院改革ガイドライン」に基づいて策定した「中東遠総合医療センター改革プラン」についてご紹介します。
「公立病院改革プラン」とは?
「公立病院改革プラン」とは、地域医療の確保のため重要な役割を担っている公立病院の多くが、医師不足や医師不足に端を発する経営悪化などにより医療提供体制の維持が厳しい状況となったことから、平成19年12月に総務省が発表した「公立病院改革ガイドライン」に基づき、医療体制の充実や経営形態の見直しなどについて策定したものです。(これを「旧改革プラン」といいます。)
掛川市と袋井市はこの動きを先取りする形で、平成19年12月から病院統合協議を開始し、平成21年1月には統合新病院の建設が正式決定に至ったことから、旧改革プランでは、平成25年統合を計画書に盛り込みました。中東遠総合医療センターの誕生は、まさに旧改革プランにおける全国モデルの先駆けであったと言えます。
旧改革プランによりまして、一部の地域や病院においては、統合・再編や経営形態の変更など、一定の改善傾向が表れました。しかしながら、全国的には依然として慢性的な医師不足に悩む地域が数多く存在しており、将来の医療需要の増大に対応するためには、医療圏全体で医療体制の再構築に取り組むことが待ったなしの状況であることから、再度、総務省としては、新公立病院改革プランの策定を求めるに至ったところです。(これを「新改革プラン」といいます。)
なお、新改革プランの特徴としては、県が策定した「地域医療構想」(将来必要となる医療圏別の病床数や医療機能を定めたもの)との整合を図るものとされており、医療圏域全体での連携が特に重視されています。
中東遠総合医療センターの現状
1 入院診療の状況
| 区分 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|
| 延べ入院患者数 | 132,299人 | 155,011人 | 156,702人 |
| 1日あたり入院患者数 | 395人 | 425人 | 428人 |
| 平均在院日数 | 10.4日 | 9.6日 | 10.3日 |
| 病床利用率 | 79.0パーセント | 84.9パーセント | 85.6パーセント |
2 外来診療の状況
| 区分 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|
| 延べ外来患者数 | 261,135人 | 308,015人 | 311,698人 |
| 1日あたり外来患者数 | 1,171人 | 1,262人 | 1,283人 |
3 地域別救急搬送受入件数(受入割合)
| 区分 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,791件 | 5,774件 | 5,604件 |
| うち、掛川消防 | 3,308件(57.1パーセント) | 3,140件(54.4パーセント) | 3,225件(57.5パーセント) |
| 袋井・森消防 | 2,215件(38.2パーセント) | 2,280件(39.5パーセント) | 2,015件(36.0パーセント) |
| 菊川消防 | 108件(1.9パーセント) | 154件(2.7パーセント) | 203件(3.6パーセント) |
| 御前崎消防 | 80件(1.4パーセント) | 137件(2.4パーセント) | 117件(2.1パーセント) |
| 磐田消防 | 80件(1.4パーセント) | 63件(1.1パーセント) | 44件(0.8パーセント) |
4 財務状況
| 区分 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|---|---|---|---|
| 医業損益 | マイナス2,183,981,000円 | マイナス1,112,142,000円 | マイナス 739,800,000円 |
| 医業収支比率 | 84パーセント | 92パーセント | 95パーセント |
| 経常損益 | マイナス1,182,938,000円 | マイナス 809,093,000円 | マイナス 594,265,000円 |
| 経常収支比率 | 92パーセント | 95パーセント | 96パーセント |
| 1人1日あたり入院診療単価 | 56,452円 | 58,416円 | 60,289円 |
| 1人1日あたり外来診療単価 | 11,007円 | 12,019円 | 12,740円 |
「新改革プラン」
「新改革プラン」は、計画期間を平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間として策定しました。プラン策定における当院の果たすべき役割について、次の4つの視点からまとめました。
1「地域医療構想」・「地域包括ケアシステムの構築」を踏まえた当院の果たすべき役割
まず、地域医療構想を踏まえた当院の果たすべき役割ですが、現在、33診療科と12の医療機能のセンター化により、診療科の領域を超えた最良の医療を多角的に展開するとともに、手術や高度医療機器を用いた診断や治療など、高度医療を必要とする多くの入院患者の診療を行っています。また、平成27年8月には救命救急センターの指定を受け、多くの重症患者を受け入れていることから、引き続き、中東遠医療圏における「高度急性期」、「急性期医療」において基幹的な役割を担っていきます。
次に、地域包括ケアシステムの構築に向けた当院の果たすべき役割については、回復期や慢性期医療に対しては、関係する医療機関や介護施設等との連携をさらに強化するとともに、地域の医療従事者への研修会や人事交流を深め、地域全体の医療レベルの向上に貢献します。また、在宅医療に対しては、急性増悪時の救急受入に万全の体制で対応していきます。さらに、近隣病院や診療所との間で患者情報を共有し、迅速な治療に役立てている医療情報システム「ふじのくにネット」の更なる活用について、関係機関と検討・研究を重ねていきます。
2 5疾病5事業への取り組みについて
国が定める5疾病5事業への取り組みは、第7次静岡県保健医療計画において当院が求められている役割を踏まえ取り組んでいきます。主な方針は次のとおりです。
| 5疾病 | 当院の方針 |
|---|---|
| がん | がん治療に対して、外科的治療、放射線治療、化学的治療等の強化を図り、より質の高い集学的治療ができる体制構築を目指します。 |
| 脳卒中 | 引き続き、脳卒中領域における地域の拠点病院としてあらゆる脳血管疾患に対応します。 |
| 急性心筋梗塞 | 引き続き、一刻を争う急性心筋梗塞に対し、迅速で十分な治療ができる拠点病院としての役割を果たします。 |
| 糖尿病 | 糖尿病・内分泌内科を有する病院として、地域医療機関との連携を強化し、十分な治療、教育に継続して対応していきます。 |
| 精神 | 精神科を有する近隣病院をの連携強化とともに、認知症疾患医療センターとして、今後増加する認知症疾患への対応を強化していきます。 |
| 5事業 | 当院の方針 |
|---|---|
| 救急医療 | 救命救急センターの充実・強化への取り組みを継続し、持続可能な体制を構築するとともに、救急医療に対する市民理解の向上に努めます。 |
| 災害医療 | 災害拠点病院として緊急時の対応ができる体制を強化します。 |
| へき地医療 | へき地診療を救命救急センターとして支えることを継続します。 |
| 周産期医療 | 地域のニーズに応じた正常分娩のほか、産科救急を受け入れていきます。 |
| 小児医療 | 地域の診療所や病院との連携を継続し、推進していきます。 |
3 経営指標と収支計画
新公立病院改革ガイドラインの趣旨に沿って、計画期間内の経営指標を定めました。最終計画年度である平成32年度の主な指標は、1日あたり外来患者数(1,250人)、1日あたり入院患者数(448人)、外来診療単価(14,000円)、入院診療単価(64,000円)、手術件数(4,800件)、救急搬送件数(5,650件)、ドック・健診受診者数(12,500人)、紹介率(70パーセント)、逆紹介率(90パーセント)、などです。
また、新改革プランにおいては、健全経営の指標として策定期間内に経常収支比率100パーセント超が求められています。開院以降、これまでの財務状況は、初期投資の影響が大きいため経常収支比率が100パーセントを下回っていますが、新改革プランの取り組みを達成することにより、平成31年度以降の経常収支比率が100パーセントを超過することが見込まれます。
今後、病院経営を左右する診療報酬制度については、逼迫する国の財政の影響などから厳しい状況も予想されておりますが、引き続き、健全経営に向けて努力してまいります。
4 再編・ネットワーク化、経営形態の見直し
中東遠総合医療センターは、掛川市立総合病院と袋井市立袋井市民病院との統合病院として再編されました。今後は、引き続き、周辺の医療機関や介護施設とのネットワークを強化して、地域医療の充実を図っていきます。
また、当院は、掛川市・袋井市病院企業団立として、開院以降、順調な病院運営を行っていますので、当面は企業団立としての運営を前提に、今後、公立病院を取り巻く状況を注視しつつ最適な経営形態についての検討をしていきます。