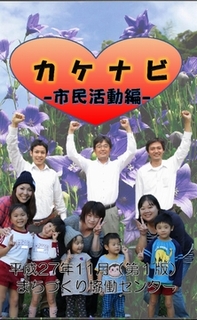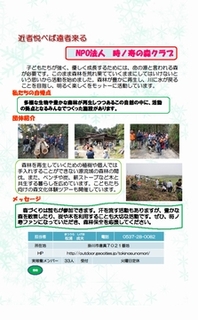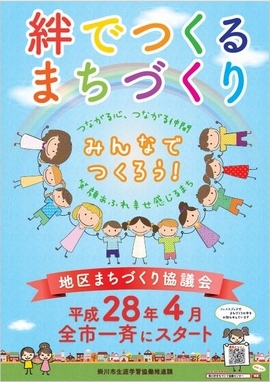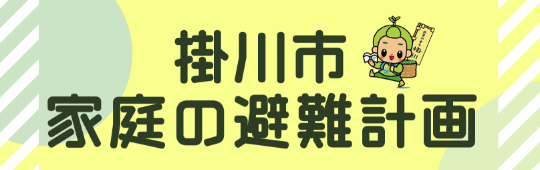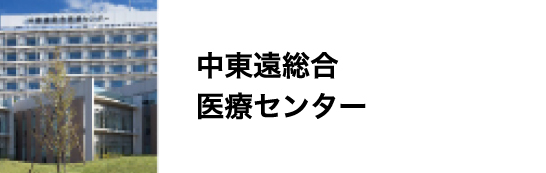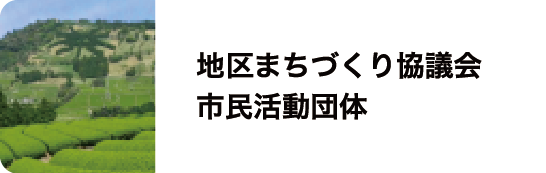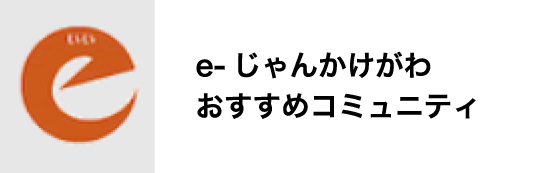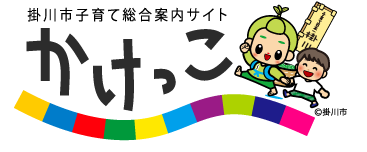掛川市協働推進課長 大石良治
現在、掛川市では地区まちづくりを進めています。まちづくり組織の両輪を「地区まちづくり協議会」と「市民団体」と位置付けしています。
まず、「地区まちづくり協議会」ですが、各地区を単位とし、区長会(自治会組織)・地域生涯学習センター(地区センター)・地区福祉協議会を中心として、地域内の様々な組織の力を結集する取り組みをしていただいております。
また、「市民団体」については、現在、NPO法人21団体と市民活動団体21団体に活躍していただいております。特に、NOP法人では9年の歳月をかけ8万本の植樹活動が評価され先日、林野庁長官賞を受賞した「時ノ寿の森クラブ」の団体があり、常に先進的な活動をしていただいております。
この2つのまちづくりの両輪について紹介させていただき、理解を深めていただきたいと思います。
最初に、11月1日(日曜日)に始めて交流会を開催した「市民団体」について紹介させていただきます。
市民団体
7月に市内42の市民団体の協力をいただき、団体紹介用冊子「カケナビ 市民活動編」の作成を行いました。市民団体がどの様な活動をしているのか、興味をもった方に、活動目的別索引により分かりやすくひとつにまとめたものであります。
今後、このカケナビの「地区まちづくり協議会編」や「人づくり編」を作成し、情報発信していきたいと思っています。乞うご期待!
この冊子の内容については、掛川市公式HPに掲載されていますので是非ともご覧下さい。
市民活動団体紹介冊子
今後、このカケナビの「地区まちづくり協議会編」や「人づくり編」を作成し、情報発信していきたいと思っています。乞うご期待!
今回の交流会は、市民団体の方々にお集まりいただき、掛川市の協働アドバイザーの川端務夢氏から人材の確保や活動資金調達などを各団体の強みや弱み、連携の可能性等についてアドバイスいただき、その後ワークショップ形式で話し合いがされました。

川端アドバイザー

ワークショップ
活発な意見交換がされ、発表後には早速、団体同士の連携が話し合われ、この交流会を今後も続けてほしいとの発言が多く出され担当者ともども大変うれしく思っています。
今後、この交流会は、地区まちづくり協議会や企業関係者などの参加も視野にした取り組みへと考えています。

発表

市民団体のみなさん
地区まちづくり協議会
次に、地区まちづくり協議会について現状を紹介させていただきます。
昨年度モデル地区として3地区が設立をされました。現在各種事業に取り組んでいただいております。本年4月以降に3つの協議会が立ち上がりました。
一昨年から多くの会議などを経て総会の開催となりました。

5月24日 曽我地区

5月31日設立 西南郷地区

7月4日設立 大坂地区
現在、その他の各地区においてさまざまな形でアンケートを実施していただいたり、ワークショップにより良い点や課題点などみんなで話し合いがされています。現在、設立に向け、課題点など掘り起こし作業結果をまとめ、それぞれに地域の特性にあった協議会の設立に取り組んでいただいております。
以上、両輪である地区まちづくり協議会と市民団体の状況を紹介させていただきました。



市民主体、行政参加
この両輪である二つの大きな組織体が、今、大きく動こうとしています。担当部署として感じていることですが、「市民主体で行政参加」の意識をもって取り組む必要を感じています。
真に地域や市民団体と手を取り合って行くためには、行政側の機構改革と職員の意識改革が必要であると考えられます。
現在、市役所内ではこの地域調整窓口(協働推進課)の一本化を図り、庁内業務の流れの改革、地域担当制の導入などについて動き始めています。これから、行政から地域への働きかけは、従来型の「地域依頼事項」を脱し、地域サポートの役割がまちづくりの大きなウエートを占めていくのではないかと考えています。
市民の皆さまからみて、地域や市民団体と行政との関係が今回の市民団体との交流会や地区まちづくり協議会の設立により整理され、今回の取り組みを「地域への関心を高め、よりよい暮らしづくりに参加する好機」として捉えていただければと思っております。