モデルコース概要
東海道五十三次は、江戸時代に整備された五街道のひとつで、江戸日本橋から京都三条大橋に至る東海道に置かれた五十三の宿場を指します。
掛川には、「掛川宿」と「日坂宿」の2つの宿場があり、多くの人が往来していました。道中には名所旧跡が多く、浮世絵や和歌・俳句の題材にもしばしば取り上げられ、掛川の「日坂」も浮世絵師歌川広重に描かれています。
歴史を肌で感じながら東海道を歩いてみませんか?
なお、日坂宿本陣跡から小夜の中山公園へ登る箇所(地名:沓掛)は大変傾斜が急なため、車は通れませんのでご注意ください。
掛川には、「掛川宿」と「日坂宿」の2つの宿場があり、多くの人が往来していました。道中には名所旧跡が多く、浮世絵や和歌・俳句の題材にもしばしば取り上げられ、掛川の「日坂」も浮世絵師歌川広重に描かれています。
歴史を肌で感じながら東海道を歩いてみませんか?
なお、日坂宿本陣跡から小夜の中山公園へ登る箇所(地名:沓掛)は大変傾斜が急なため、車は通れませんのでご注意ください。
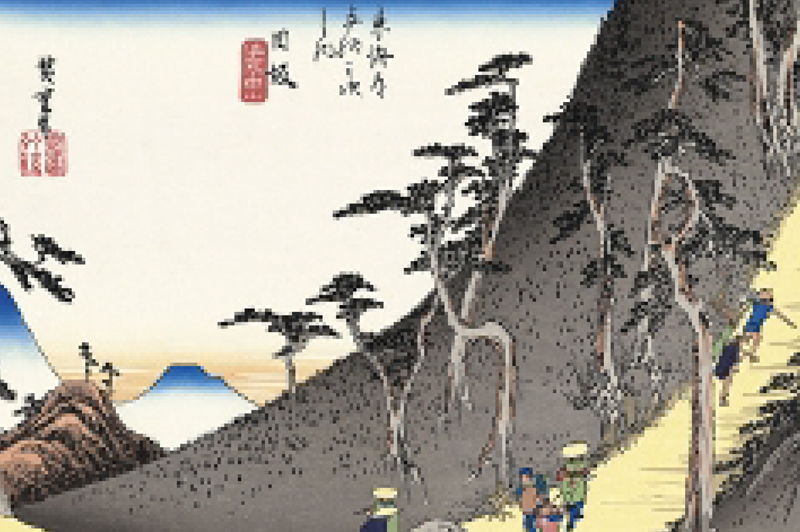
歌川広重 「東海道五十三次 日坂」
ルートポイント紹介
1
間の宿「原川」・金西寺
原川は掛川宿まで1里18町(約6キロメートル)、袋井宿へ33町(約3.6キロメートル)の位置にある「間の宿」でした。
間の宿では、旅人の休息の場を提供することはできますが、旅籠の営業は許されていませんでした。しかしながら、金西寺の原川薬師と呼ばれる阿弥陀仏へ供えるための薬師餅を売る茶屋や酒屋などが軒を連ね、賑わっていたようです。文化・文政頃の集落戸数は、46軒と伝えられています。
間の宿では、旅人の休息の場を提供することはできますが、旅籠の営業は許されていませんでした。しかしながら、金西寺の原川薬師と呼ばれる阿弥陀仏へ供えるための薬師餅を売る茶屋や酒屋などが軒を連ね、賑わっていたようです。文化・文政頃の集落戸数は、46軒と伝えられています。
2
間の宿「原川」・金西寺

原川は掛川宿まで1里18町(約6キロメートル)、袋井宿へ33町(約3.6キロメートル)の位置にある「間の宿」でした。
間の宿では、旅人の休息の場を提供することはできますが、旅籠の営業は許されていませんでした。しかしながら、金西寺の原川薬師と呼ばれる阿弥陀仏へ供えるための薬師餅を売る茶屋や酒屋などが軒を連ね、賑わっていたようです。文化・文政頃の集落戸数は、46軒と伝えられています。
間の宿では、旅人の休息の場を提供することはできますが、旅籠の営業は許されていませんでした。しかしながら、金西寺の原川薬師と呼ばれる阿弥陀仏へ供えるための薬師餅を売る茶屋や酒屋などが軒を連ね、賑わっていたようです。文化・文政頃の集落戸数は、46軒と伝えられています。
3
間の宿「原川」・金西寺

原川は掛川宿まで1里18町(約6キロメートル)、袋井宿へ33町(約3.6キロメートル)の位置にある「間の宿」でした。
間の宿では、旅人の休息の場を提供することはできますが、旅籠の営業は許されていませんでした。しかしながら、金西寺の原川薬師と呼ばれる阿弥陀仏へ供えるための薬師餅を売る茶屋や酒屋などが軒を連ね、賑わっていたようです。文化・文政頃の集落戸数は、46軒と伝えられています。
間の宿では、旅人の休息の場を提供することはできますが、旅籠の営業は許されていませんでした。しかしながら、金西寺の原川薬師と呼ばれる阿弥陀仏へ供えるための薬師餅を売る茶屋や酒屋などが軒を連ね、賑わっていたようです。文化・文政頃の集落戸数は、46軒と伝えられています。


