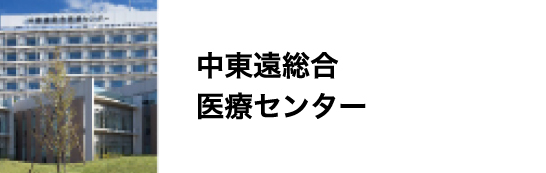被保険者の世帯で、後期高齢者医療制度と介護保険制度の両方の制度で自己負担額があり、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が下記の限度額より500円を超える場合、申請により高額介護合算療養費が後日支給されます。
※ 支給対象者には、市役所から申請書を郵送します。
対象となる世帯
同じ世帯で、医療費と介護サービス費の両方を支払い、合算した年間の自己負担額が限度額より500円を超えた世帯が対象となります。
ただし、同じ世帯でも加入している保険(国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度)ごと別々に合算します。そのため、夫婦であっても一方が国民健康保険、もう一方が後期高齢者医療制度に加入している場合は、合算することができません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)
| 所得区分 | 自己負担割合 | 後期高齢者医療制度+介護保険の 自己負担限度額(年額) |
| 現役並み3 | 3割 | 212万円 |
| 現役並み2 | 141万円 | |
| 現役並み1 | 67万円 | |
| 一般2 | 2割 | 56万円 |
| 一般1 | 1割 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 | |
| 低所得者1 | 19万円 |
所得区分に関しては後期高齢者医療制度についてを参照してください。
注意点
自己負担額は、高額療養費または高額介護サービス費が支給されている場合は、その支給された金額を差し引いて計算します。
同じ世帯であっても、後期高齢者医療制度の被保険者以外のかたの自己負担額は合算されません。
高額介護合算の計算上、支給額は後期高齢者医療制度及び介護保険からの合計額で算出されますが、実際の支給は、医療・介護で按分し、個人ごとに振込が行われます。
後期高齢者医療制度及び介護保険からそれぞれ振込が行われるため、医療と介護では支給日が異なります。
※ 低所得者1の世帯は、合算の限度額(19万円)が高額介護サービス費の限度額(約30万円)「世帯利用者負担上限24,600×(掛ける)12か月」を下回る事態が生じるため、両制度の整合性を確保するため、医療保険は原則どおり低所得者1(19万円)の限度額で支給額を計算した後、介護保険において低所得者2(31万円)の限度額で支給額の再計算を行います。